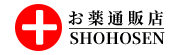睡眠の質を上げる10のコツ
睡眠は複雑な生理的プロセスであり、人の生命に不可欠なものです。睡眠の質は健康と密接に関係しており、睡眠障害は多くの病気を引き起こす重要な要因の一つとされています。数多くの研究や臨床実験によって、睡眠障害と心理的な問題、精神疾患は相互に影響を及ぼし合うことが明らかになっています。
人の一生の約3分の1は睡眠に費やされるため、その重要性は明白です。研究によると、若者、中年層、高齢者を問わず、就寝時間と起床時間が安定している人ほど、睡眠の質が高い傾向にあります。睡眠の質が良い人は、より良い気分を保ち、精神的なパフォーマンスが向上し、学習成績も優れることが分かっています。

良い睡眠とは?
01. すぐに入眠できること
夜、電気を消して布団に入り、スマホを置いた後、10~20分以内に眠りにつくことが理想的です。
02. 睡眠に一定の深さがあること
深く安定した呼吸で、途中で目が覚めにくいことが大切です。
03. 夜中に目が覚めないこと
または、夜中に起きる回数が2回未満で、夢から突然目覚めることがなく、目覚めた後に夢をすぐ忘れるのが良い状態です。
04. 朝の目覚めがスムーズであること
朝、すっきりと目覚め、エネルギッシュで気分が良く、日中に眠気を感じず、頭が冴えていて仕事の効率が高いことが理想的です。
しかし、現実には多くの人が以下のような睡眠の悩みを抱えています。
寝返りを何度も打ち、なかなか眠れない。
深夜3~4時に目が覚めてしまい、その後眠れなくなる。
睡眠の質が悪い場合、どうすればいいのでしょうか?
不眠の症状とは?
通常、不眠とは、十分な睡眠時間があるにもかかわらず、長時間の入眠困難、頻繁な目覚めや目覚めた後の再入眠困難、睡眠の質の低下、持続的な睡眠時間の減少などが見られる状態を指します。簡単に言うと、寝るための十分な時間と適切な環境が整っているのに、眠れないことを指します。不眠にはさまざまな症状があり、一般的には「寝つけない」「眠れない」「眠りが浅い」という形で現れます。具体的な症状は以下の通りです。
01. 入眠困難
ベッドに入ってから眠りにつくまでに30分以上かかる。
02. 目覚めやすい
夜中に何度も目が覚める、または目が覚めた後に長時間覚醒している。
03. 睡眠が浅い
睡眠の深さが足りず、周囲の音や物音に気づくことがある。
04. 多夢
一晩中夢を見ているように感じる、特に悪夢が多く、悪夢から目が覚めることが頻繁にある。
05. 早朝覚醒
朝、通常より1時間以上早く目が覚めてしまう。
06. 睡眠時間が短い
成人が一晩に5時間未満の睡眠しか取れない。
07. 休養感が得られない
一晩寝て朝を迎えても、日中に疲れを感じたり、エネルギーが不足していると感じる。
睡眠が良くないことは、体内に毒をため込んでいるようなものです。

研究者は約1000人のボランティアに対してスクリーニングを行い、毎晩7~9時間の睡眠時間を確保できる健康な女性35名を見つけました。その後、これらの参加者をランダムに2つのグループに分けました:
第1グループ:6週間の十分な睡眠段階(毎日7~9時間の睡眠を確保)
第2グループ:6週間の軽度の睡眠削減(寝る時間を1.5時間遅らせ、起床時間はそのまま)
その結果、十分な睡眠を確保した期間と比較して、睡眠時間が削減された第2グループの内皮細胞の酸化ストレスレベルは78%増加しました。これにより、わずかな睡眠の減少でも長期的には深刻な影響があることが示されています。専門家は、長期間の睡眠不足が内皮細胞の酸化ストレスレベルを上昇させ、体内の微小環境に炎症を引き起こすと述べています。血管内皮細胞の炎症と機能不全は、心血管疾患の発症初期に見られる現象であり、これは長期間の睡眠不足が心臓病のリスクを高めることを示唆しています。睡眠不足は「毒素」を蓄積させ、良好な睡眠はそれらを「排毒」するのです。
健康的な睡眠のための10の方法
世界睡眠協会は、健康的な睡眠を実現するために以下の10の方法を推奨しています:
1.毎晩決まった時間に寝る、そして決まった時間に起きる。2.昼寝をする習慣がある場合、昼間の睡眠時間は45分を超えないようにする。
3.就寝前4時間は過剰なアルコールを避け、喫煙もしない。
4.就寝前6時間はカフェインを避ける(コーヒー、紅茶、ソーダ、チョコレートなどを含む)。
5.就寝前の軽食は許容されますが、重い食事や辛い食べ物、甘い食べ物は就寝4時間前に避ける。
6.定期的に運動をするが、就寝前の激しい運動は避ける。
7.快適な寝具を使用する。
8.寝室の温度を適切に設定し、通気を良く保つ。
9.外部の騒音や光害を排除する。
10.ベッドは睡眠のためだけに使用する。オフィス、作業室、または娯楽室として使用しない。

いびきは病気、ただの熟睡ではない
多くの人々は、いびきは「良い睡眠をとっている証拠だ」と考えがちですが、実際はそうではありません。いびきは呼吸停止症候群という病気で、睡眠の質を損なうだけでなく、最悪の場合、突然死のリスクもあります。 以下の特徴が見られる場合、それは呼吸停止の可能性があります:
1.いびきが非常に大きく、隣の部屋まで聞こえる。2.いびきの音が不規則で、通常の仰向けの寝姿勢や飲酒後のいびきは比較的軽く均一ですが、呼吸停止を伴う場合、いびきが突然止まり、数十秒後に再び深い音が出ることがある。
3.家族が「息が詰まって汗だくになり、腕や足を伸ばしている」といった症状を頻繁に見かけるが、体をひねるとすぐにいびきが再開される。 また、寝ているときに口が乾き、枕元に水を置いておくことが多い場合、それは呼吸停止症候群による口呼吸の影響である可能性があり、注意が必要です。
臨床調査によると、睡眠時呼吸停止症候群は40歳前後の若年層に多く見られ、65歳以上ではむしろ少なくなります。なぜなら、この年齢層は仕事や飲み会、出張で遅くまで起きていることが多く、運動不足やストレスによる肥満などが原因となっているためです。
睡眠時呼吸停止症候群は子供にも多く見られます。こうした子供たちは一般的に痩せ型で、胸骨が外向きに出ており、鼻水をよく流し、口呼吸をしていることが多いです。これらはすべていびきと関連があります。多くの子供たちは扁桃腺が腫れて、咽頭を圧迫して空気の通り道を塞いでおり、これにより鼻炎や副鼻腔炎などの病気が慢性化し、長期にわたる口呼吸が顎の発育に悪影響を与え、顔面が変形することがあります。これを「アデノイド顔貌」と呼び、子供の容姿にも影響を与えます。
また、いびきや口呼吸により、子供たちは夜間に酸素不足になり、日中に疲れを感じたり、集中力が欠けたりすることがあります。いびきが深い睡眠を妨げることで、本来深い睡眠(徐波睡眠)で分泌されるべき成長ホルモンが減少し、成長や発達が遅れることがあります。
幼い子供たちが睡眠時呼吸停止の兆候を早期に発見することは、早期治療において非常に重要です。親は、子供が寝つきが悪かったり、汗をかいたり、時々いびきをかいたり、無声になった後に身体を動かしたり、尻を突き出して寝ることがあれば、呼吸停止の可能性があるので、注意深く観察することが大切です。